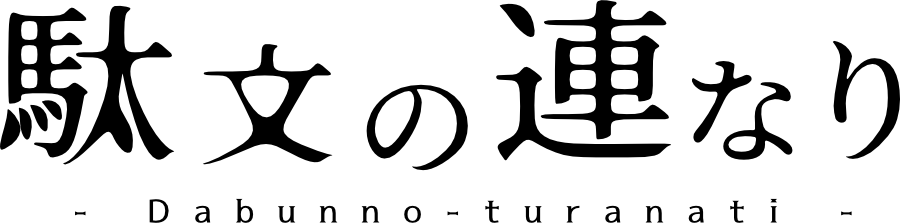「明日のお天気です。名古屋は、十日ぶりの晴れ間が戻り、絶好の洗濯日和となるで……」
テレビからは、淡々と天気予報が垂れ流されている。八月も終わりという季節柄、雨が降るのは仕方のないことにしても十日連続とは、降りすぎじゃないかと天に異を唱えたくなった。おかげで、夏休みの課題に向き合う生活が続き、精神が非常に困憊している。
「ねえ、そうちゃん。」
目の前には、鉛筆を咥え項垂れたように数学のテキストの上に顔を落としている幼なじみがいた。
「私さ、ずーっと昔から、高速道路の上に家建てたいって、言ってるでしょ?」
ぼつぼつと、降り続いている雨と同じリズムで、言葉が降ってくる。残念なことに僕の幼なじみは少し変わっており、昔から「高速道路の上に家を建てたい」と事あるごとに口にしていた。
「それでさ、もうそろそろ実行に移したいなーと思ってて。」
爽太郎が話さない間も、言葉の雨はぽつぽつと、降り続いていた。本から顔を上げ窓の外を見ても、雨は降り続いている。花菜は中学生にもなって一体何を言っているのだろうか。机に置かれた数学のテキストと同じように、爽太郎には彼女の思考を理解できなかった。
「でさー。明日、晴れじゃん。久しぶりにさー、外に出て、やってみない?」
しがしがと、鉛筆を噛む彼女の癖は昔からだ。しかしまさか、神様が曇天を追いやった後に、こんな大きな雷雲が来るとは。これが入道雲のように美しかったら良かったのに。
「そうちゃん、やらない?」
花菜は数学のテキストの紙面から顔を上げると、爽太郎の方を見つめた。その双眸には、まるで星空のようにキラキラと、無数の星が浮かんでいた。爽太郎は、それを一つ一つ潰してまともにしてやろうかと考えたが、あまりにも現実的ではないため辞めることにした。
現実的と言えは、そろそろ彼女の質問に返答しなければならない。爽太郎はそう考えることもなく、答えを出した。
「やるわけないだろ。」
一言、彼女に言葉を投げると、爽太郎はまた、手に持った本の世界に戻った。
クリーム色の紙面とゴシック体の文字の羅列に、集中が戻ってくる感覚がする。
不意に、先程の彼女の言葉を思い出した。
そんなことができるわけないだろう。本の中じゃあるまいし。
翌日、名古屋の空は見事なまでの晴天だった。爽太郎は、十五人分の洗濯物を庭の物干し竿へ干し終わると、朝食を食べにロビーまで戻った。
「そうちゃん、お疲れ様。」
両手に朝食が乗っているお盆を持ち、花菜が歩いてくる。お盆の上にはハムエッグと小盛りのサラダ、トースト2枚が乗っていた。
ゆっくりと机に置くと、花菜は椅子に座り、「いただきます」と言い、朝食を食べ始めた。
爽太郎も花菜の隣に座り、同じく「いただきます」と言い、朝食を食べる。十五人もいると、食事時のダイニングテーブルは戦場となる。一仕事終えるとあらかた戦は片付いており、こうして優雅に朝食が食べれるのだ。
「それでさ、そうちゃん。」
トーストにイチゴジャムを塗りながら花菜が切り出した。甘い香りが爽太郎の胃を収縮させる。
「私は今日やるために動くけど、どうする?」
きっと彼女がやろうと言ったのは昨日のあれだなと思いだし、少し眉を顰めた。彼女は本当にやるつもりなのだ。女子の方が精神的な成長は早いと聞くが、それは嘘なのかも知れない。世間の知識とは当てにならないものだな、と少し肩を落とした。
「莉子とか一夏とか呼んでさ、学校の皆で、準備してみようと思うんだけど。」
ジャムを塗り終わったのか花菜はトーストに囓りついた。サクっと、小気味の良い音が鳴った。
「だいたい、やるったって、どうするんだよ。高速道路の上に家を建てるって。」
爽太郎は二枚のパン両方にマーガリンを塗り終わると、純粋な疑問を花菜にぶつけた。
「ひゃんぴんぐはーうぉ、ふぁしのううぇにとめふの。」
パンを口に含みながら話す花菜の言葉は、多分聖徳太子でも聞き取れないだろう。
「なんて言った?」
「だから、キャンピングカーを高速の橋の上に止めるの。」
咀嚼し終わったのか飲み込むと、理解のできないことを流暢に言い始めた。彼女はこの想像力を使えば作家になれるのではないだろうか。花菜の将来に、一筋の希望が放たれる。
「無理だろ。高速の上は基本的に駐車禁止だし、第一、キャンピングカーはどうするんだ。」
彼女は少しばかり現実的にならなければなるまい。これは爽太郎からのささやかなプレゼントだ。これできっと、花菜は難解なことを言い出すのを辞めるはずだ。
「大丈夫、アテはあるし、きっとなんとかなるよ。」
現実はそう単純ではなく、花菜は止まらなかった。
一体、彼女の何がそんなにもこの理解しがたい夢に向かわせるのだろうか。
「で、そうちゃんもやるでしょ、暇だし。」
暇だし。それを言われれば仕方ないな、と思った。特にこれといった用事はなく、連日の雨で鈍った体を動かすには丁度良いかな、なんて爽太郎は軽く考えていた。
「まぁ。確かに暇だし、やるよ。」
花菜は爽太郎の言葉を聞くと「やった!」とガッツポーズを決めていた。雨が僕たちに時間を与えたばっかりに、夏休みの終わりをこんな意味不明な夢に向かわせた。
面白くなってきたな、と爽太郎は内心胸躍っていた。
朝食を食べ終えるとハウスから花菜は駆けだしてゆき、同級生の家々を回って、近くの緑地へと皆を集合させた。
面々を見てみる。花菜の友達の莉子と一夏に、爽太郎の親友の直竹の姿までそこにあった。
「おはよ、爽太郎。」
眠そうな目を擦りながらそこに立っている直竹に、少し懐かしさを覚えた。あんなにも夏休み中遊んだのに、数日遊ばないだけでこんなにも懐かしくなるものなのかと感傷的な気持ちになる。爽太郎がそんなことを思っている間も、直竹は眠そうにぼーっと突っ立っていた。
「直竹も呼ばれたのか。」
「もち。こんな面白そうなこと、手を出さないわけないっしょ。」
少し、眠さを取り払ったのか段々と声色が上がっていっているように感じる。
「じゃ、皆揃ったね。」
こっちを確認した花菜は皆の前に立つと、こほん、と咳払いしてから、話し始めた。
「もう知っていると思うけど、私の夢は『高速道路の上に家を建てること』なの。今日は、それをやってみたいと思う。だからお願い、皆の力を貸して。」
そう言って花菜は胸の前で手を合わせて懇願した。眉を顰め真っ直ぐな双眸からは真剣さを感じる。彼女はそこまで本気なのか、と改めて実感させられた。
少しの間、花菜の言葉を理解する必要があったらしく、暫し沈黙が朝の緑地に訪れた。
朝特有の涼しげな風が吹いている中、最初にその沈黙を破ったのは、直竹だ。
「もち。手を貸すよ。ちょっと理解に時間がかかったけど、面白そうだしな。」
直竹はやっと本調子が出てきたのか「よしっ」と頬をパシッと叩いた。
次に話し始めたのは花菜の友達の莉子だった。
「私も、できる限り手を貸すよ。花菜ちゃん、初対面の時そのことばっかり話してたもんね。」
花菜の学校での素性が明かされ、爽太郎は衝撃を受けた。おいおい、花菜は学校でも同じこと言ってるのかよ。花菜は、本当に変わった幼なじみだ。それは、爽太郎の想像の上をいく、本当に変わった幼なじみらしい。認識が、より重い方へ変わっていく。
「わ、私も手を貸すわ。言ってる意味は分からないけど、皆がやるのであれば。」
最後に話したのは一夏だった。花菜の言葉の理解には乏しそうだが、うんうんと頷いていた。
「み、みんなぁ……。」
花菜は感激のあまり瞳が潤んでいた。よほど嬉しいのか、頬が赤く染まっている。
「よし、とりあえずやってみようぜ。な、花菜。」
最後に直竹が場をまとめ、皆の士気は上がっていた。最後に持って行くのはいつもこいつだったな、と夏休みが始まる前の学校を思い出した。
「えっと、花菜ちゃん。なにすればいいの?」
莉子が花菜に指示を仰いだ。花菜は顔を元の色に戻し、口を開いた。
「とりあえず、必要なものはキャンピングカーと食料だけだよ。キャンピングカーにはアテがあるし。」
「その、高速までの運転手とかはどうするんだ。大人のアテもあるのか?」
実はこの中で一番現実を見れている直竹が質問を飛ばす。
花菜は直竹の質問を咀嚼するように飲み込むと、何も考えていないような顔で口を開いた。
「運転手は、私たちの誰かがすればいいよ。」
花菜の言葉に、皆、ぽかんとしていた。さすがに、十四歳のガキでも、免許証の存在は知っているし、持っていない者が運転したら捕まることも周知の事実だ。そのことを知っていて言っているとしたら、もしかして花菜は、思考が一周二周回った変人なのではないだろうか。爽太郎の花菜に対する心証はどんどんと、暗くなっていく。
「えっと、花菜ちゃん?」
莉子は花菜に「何を言っているの?」と訴えるような顔で言った。というかよく見れば全員が、同じ顔をして花菜を見つめている。
暫し沈黙の後、一夏がこのいたたまれない空気感を感じ取ってか口を開いた。
「……まぁそれは一旦置いとくとして、花菜。キャンピングカーのアテとはなんなの?」
「キャンピングカーはね、ほら、学校の近くに廃墟があるでしょ。そこの敷地内に、キャンピングカーが乗り捨てられてたの。」
花菜の話に爽太郎は少し考えた。爽太郎たちが通っている学校の近くには確かに、無駄に敷地の広い廃墟がある。昔、その廃墟に皆で集まり、肝試ししたのを思い出した。まさかその廃墟にキャンピングカーが乗り捨ててあるとは。そんな都合のいい話があるのか?
「乗り捨てられてたって、鍵とか付いていないかもだし、それに動かないかも知れないよ?」
「だから、それをそうちゃんたちに見に行ってきてほしいの。お願いできる?」
花菜は潤む瞳で、爽太郎に懇願した。
直竹は、花菜の話を一通り聞いて、少し考え込んでいた。誰のか分からないキャンピングカーを拝借し、あまつさえ動かそうと言うのだ。普通は、実現不可能だろう。
「そのうちに、莉子と一夏と私で、食料調達。それでどう?」
「うーん。分かった。とりあえず、キャンピングカーのことは俺と爽太郎に任せろ。」
「じゃ、またここで集合ね。時間は、三時間後くらいで大丈夫?」
「多分、大丈夫だ。」
「じゃ決まりね。それでは、解散!」
花菜の解散の一言の後に爽太郎は直竹に連れられて、緑地を抜けた。何故かもうすでにものすごい疲れた気がするのは、気のせいだろうか。
「なぁ、お前の幼なじみはいつもあんなことやっているのか?」
直竹は不思議そうな顔で、爽太郎を見た。
「昔から男勝りで、一人で秘密基地作り始めたりはしてたけど、まさかあそこまでとは僕も知らなかったよ。」
「そうか。花菜は面白い奴なんだな……。ま、とりあえずあの意味不明な計画がどこまで実行できるか分からないが、俺はできるところまで手を貸すぜ。」
直竹の顔は、少し考え込むと、妙に誇らしげな顔をした。彼もつくづく、お節介好きだなと少しばかりため息が漏れる。
「とりあえず、廃墟に向かうぞ。」
そういってずんずんと歩みを進めた。この緑地から、その廃墟までは歩いて十五分ほどかかる。夏休みの課題の話とか、諸々を話しながら歩いて行くと途中、面白い人に会った。
「おはよう、直竹、だっけか。最近は忘れっぽくてな。数日会わんだけでこれだ。」
「お。大熊のじいちゃん。おはよう。朝から元気だね。」
「おはようございます。」
「おお、爽太郎もおったか。年寄りの朝は早いものでな、こうして朝早く起きて、女子の観察をせねば、元気がでん。」
そういうと腕を上下に振り、元気そうなアピールをした。この人は通学路に面した住宅地の古い家屋に住んでいる、大熊のじいちゃん。昔から、この地域に住んでいて、いらぬ知識や猥談を、この地域の男子学生に吹き込んでいる風変わりなじいさんだ。
「今日は、散歩か?」
「いや、ちょっとした捜し物だよ。」
「そうだと思った。今時の中学生は、ゲームかデートかでしか、外に出ん。不埒なものだ。」
ほっほっほっと笑うと、軒先に置いてあったじょうろで家の前に並べられた花壇に水をやり始めた。直竹と爽太郎は大熊のじいちゃんに手を振って別れると、先を急いだ。
「やっぱり、大熊のじいちゃんは面白いな。あの人に会うと、元気になった気がする。」
「確かに。じいちゃんはいつまでああして女子観察を続けるんだろうね。」
「そりゃ、永遠さ。俺もそうやって生きていけたら、幸せだろうな。」
大熊のじいさんは、世の男子に元気を届けてくれる魔術師かも知れない。そう思うと、なんだかあの人もすごい人なんだな、と思った。
そこから、住宅地を抜け、田んぼと、空き地が点在している地域に着いた。ここまで来れば、廃墟は目と鼻の先だ。
「よし、あとちょっとだ。と、その前に一休みしないか。」
そう言って、路肩のバス乗り場のベンチに腰掛けると、直竹ははぁ、と肩の力を抜いた。
「なぁ爽太郎。花菜をあんなことに縛り付けているのは一体何なんだろうな。」
「さあね。分からないよ。単に突発的な発想かも知れないし、単に暇なだけかも知れないし。」
「ま、そうか。そんなもんだよな。」
二人は会話を終わらせると、目の前の田んぼに意識を向けた。少しの風で波立つ田んぼに、少しばかりの涼を感じる。近くの森からは、ツクツクボウシの鳴き声も聞こえてきた。
実は、爽太郎は何故あんなにも花菜がこの変わった夢に熱中するか知っている。だが、それは直竹には教えられない、二人だけの秘密だ。ともかく何も言わず手伝ってくれる直竹は、やっぱりいい人なんだな、と再認識した。
「よし、元気も回復したことだし、いくか。」
直竹は立ち上がると、廃墟の方を見た。錆びた鉄と、黒ずんだ木が見え隠れするその廃墟は、本当にお化け屋敷の形相をしている。
爽太郎も立ち上がると意を決して、廃墟の方へ進み始めた。
草木が膝の位置まで生え茂り、その中にぽつんと、倒壊しかけの廃屋が建っている。周りは灰色のブロック塀に囲まれており、余計に雰囲気を醸し出している。
「失礼しま~す。」
直竹は小声で挨拶すると敷地内に忍び足で入っていく。爽太郎もまさか、中二にもなってこんな小学生じみたことをやるとは思わず、少しの緊張と、久しぶりの高揚感が相まっていた。
「こいつは驚いた。ホントにあるとはなぁ。」
廃屋の横を曲がり、何もないだだっ広い庭に出た時、それは確かに目の前にあった。
クリーム色の塗装が所々剥げた車体に、フロントガラスには蜘蛛の巣が張っている。廃屋と見比べても新しく、そして大きい車体が、そこにはあった。
「本当にあるんだね……。」
一体、花菜は何をしたらこんな大きな物を陰に隠れた廃墟から見つけられるのだろうか。どんどんと、花菜に対する不信感が募ってくる。彼女は一体、何者なのだ。
「よし、爽太郎。中見てみよう。」
直竹はそう言うと運転席側のドアを開け、車内を見渡した。
「はは、これは笑うしかねぇわ。爽太郎、これは何なんだと思う。」
直竹の手に握りしめられていたのは、この車のものと思しき、青色の鈴の付いた鍵だった。
「これは想像の範囲外だね。」
「しかもな、スピードメーターのところを見てみると、燃料が少し残ってるぞ。こいつはワンチャン、エンジンが動けば走り出すかも知れない。」
どんどんと、二人の間に不穏な雰囲気が現れる。そもそも、このキャンピングカーは何なのか。
どんどんと湧く疑問に、恐怖と、高揚感が湧いてきた。これは、面白い展開だ。
「とりあえず、後ろの生活するところも開けてみようぜ。」
計り知れない直竹の好奇心に、すごい奴だ、とまたも感じさせる。
ガラガラガラ。立て付けが悪いのか、開けるときに滑車から音がしたものの、スムーズに開いた。ドアの向こうには、ホコリや蜘蛛の巣をかぶった、生活できるスペースが広がっていた。よく見ればソファーや小さなコンロなども揃っていて、これがあればどこでも生活ができそうだ、と爽太郎は思った。ハウスにある自分の部屋よりも良いくらいだ。
すべてが疑問で混乱してくる中、あらかた調べてから、一旦外に出ることにした。
「なぁ、爽太郎。花菜は一体、何者なんだ。」
爽太郎の頭の中は、疑問に埋め尽くされていて何も答えられなかった。
その間もツクツクボウシは叫ぶように、耳元でやかましく鳴いていた。
「とりあえず、一旦戻ろうぜ。車のキーを拝借していけば、この車は動かないし大丈夫だろ。」
小指に鈴を引っかけくるくると振り回す。りんりんと、錆び付いた音色が、廃墟に響き渡った。
「この車は、誰の物なんだろうね。」
帰り道、爽太郎と直竹は歩きながら一つ一つの疑問について話したが、一向に何の回答も出てこなかった。ただ分かったことは花菜は変わり者だということと、どこに行ってもツクツクボウシは鳴き続けているということだけだった。
爽太郎の腕に巻かれた腕時計は、正午を指していた。歩き疲れた二人は、空腹で元気を失っていながらも、なんとか緑地へとたどり着いた。
「お、丁度良く来たね。」
先程の場所まで戻ると、花菜たちがリュックサックを二つ、それと木製のバスケットを新たに抱えながら、待っていた。
爽太郎たちがバテたように芝生の上に座り込むと、一夏が「体力なさ過ぎよ!」と煽りを入れてきた。夏休みはほぼ屋内でゲーム三昧をしていた僕たちにとって、これは久しぶりの運動なのだ。体力なんて、元より微塵もない。
「とりあえず、お昼にしよっか。」
莉子は手に持っていたバスケットを爽太郎たちの目の前に置くと、蓋を開けた。中には彩りの豊かなサンドイッチが詰まっていた。
花菜と一夏が芝生の上にブルーシートを広げると、爽太郎たちは各々シートの上に座り、サンドイッチを手に取った。
ぱくっ。一口頬張る。パンの中からみずみずしいトマトの果汁が溢れ出し、爽太郎たちの疲労をすぐさま吹き飛ばしていった。その後は、食欲に駆られた男子中学生である。手を止めることなくパクパクと食べ続けていた。
「おいしい。」
意識がサンドイッチにしか向いていない中、爽太郎が感想を述べた。
「本当? 嬉しい。私たち三人で作ったの。」
莉子は手にサンドイッチを持つと、小さい口に入るように、小さく頬張った。
よくよく考えれば、同じクラスの女子の作った手料理を一緒に食べ、ピクニックをしている。これは言わばデートなのではないだろうか。爽太郎は心の中で花菜にほんのりと感謝した。
「ねぇ、直竹君、おいしい?」
莉子が直竹に聞きに行った。昔、直竹から莉子に気を向けられているという話を聞いたことがあったけど、まさか本当のことだったとは。直竹は嬉しそうに「おいしい」と言って笑っていた。まんざらでもなさそうだ。
サンドイッチも綺麗になくなると、一夏がペットボトルのお茶を皆に配った。キンキンに冷えた緑茶のペットボトルからは、結露がぽつぽつと滴っている。
「それで、そうちゃんたちはどうだった?」
最初に切り出したのは案の定、花菜だ。
「俺たちのほうは花菜の言うとおり。そこにあったよ。エンジンはどうか分からないが、ガソリンは少し入ってた。花菜、あれはどうやって見つけたんだ。」
一応名目上大都会の名古屋の端のほうと言っても、キャンピングカーはそうそう落ちてはいない。この疑問は、爽太郎、直竹の中で大きなものとなっていた。
「お、良いね。あれはね、散歩してたらたまたま見つけたんだよ。たまたま。」
花菜からの回答は、二人が望んでいる物とは違ったが、正直これ以上疑いようがない。
「花菜たちのほうは?」
「私たちのほうは、準備万端よ。食料もあるし。」
そう言って一夏は傍らに置かれたリュックサックをバンバンと叩いた。
「あの、それでね、花菜ちゃん……。」
莉子が、深刻そうな顔をして、切り出した。一体何の話が待ち受けているのだろうか。
「お母さんに準備する代わりに、今日は家に戻れって言われたの。一夏と、二人。」
昔にもこういうことがあったな、と思い出した。あれも、花菜が変わったことを言い出して、それで今日と同じく皆を集めて話したときだった。
「なんで?」
花菜の顔色が悪くなるのを感じる。声色も、怒りからか少し震えているようだった。
「なんかね、施設の子とあんまり遊ぶなって。今までは無視して遊んでたけど、なんか今日は当たりが強くて。私のお母さんが一夏のお母さんにまで連絡して、止めてきたの。だから、今日はここまでで帰るね。」
久しぶりに聞いた「施設」と言う言葉に辟易する。昔から「施設」と言う言葉は嫌いだった。友達だと思っていた奴も、親友も、好きな人も、こうして「施設」と言うだけで消えていった。
「ううん。今日はありがとう。莉子たちのおかげで、なんとかできそうだよ。」
「花菜……。」
花菜は、苦虫をかみ潰したような、そんな表情でグッと我慢していた。
一夏の同情の声だけが、緑地に広がった。
「じゃ、じゃあね。花菜ちゃん、また学校で。」
早々に莉子は片付けをし、一夏と共に去って行った。もう何も感じなかった。何度も、こんなことが何度もあった。爽太郎の唯一の親友も、いつ大人に引き裂かれるか分からない。激情を超えた何かが、胸にぼんやりと蠢いていた。
「それで、どうするよ。」
この空気を変えれるのは、この場には直竹しかいなかった。
「私は、やる。この目標のために、今まで我慢してきたんだもん。直竹も帰っていいよ。そうちゃんと私だけで、やるから。」
花菜の黒い双眸には、鬼が宿っていた。邪魔されてなるものか。これが、終着点でいい。何が何でも、成功させてやる。花菜から感じ取れる感情に、その場の空気は緑地と正反対に、重く、暑苦しい物へと変貌していた。
「いや、俺は手伝うよ。何が何でも。」
手に持ったお茶を飲み干し、直竹が鬼をなだめるように、優しく言葉を投げた。
「直竹……。」
今まで色々なものに見捨てられてきた僕たちを救ってくれるのは、やっぱりこの男しかいない。
「わかったわ。直竹、本当にありがとう。でも、最後までなんて考えないで。無理になったら速攻、帰って良いから。」
花菜は直竹の手を取り、何度もありがとう、ありがとうと言った。
「それで、どうする。」
今度は爽太郎が切り出した。
「三人で、キャンピングカーに行こう。それで、高速道路の上に家を建てるんだ。」
花菜の瞳には、先程の鬼はいなく、強いて言えば、雨上がりの澄んだ青空が写っていた。
「ちょっとまて、運転手はどうするんだ。大人を連れて行くのか?」
「いや、大人は連れて行けない。どうせ私たち、逮捕されちゃうから。」
いたずらっぽく舌を出しながら言う花菜に、ちゃんと結果を知っていたんだ、と爽太郎は少しホッとした。彼女にも、しっかりとした常識があったらしい。
「そうちゃん、運転お願いできる?」
爽太郎の手に花菜はそっと、手を覆い被せると目をあわせ、お願いしてきた。
この先の結果を、爽太郎は知っている。高速の上までいき、無免許運転で警察に捕まるか、そもそもキャンピングカーが動かなくて夢半ばで終わるかのどっちかだ。それでも、爽太郎は花菜に高速の上まで行きたい、と思わされてしまった。
「いいよ。花菜の夢は、僕たちの夢だから。」
精神的に辛いときも、悲しいときも、寂しいときも、僕たちはそばにいた。一心同体の、家族以上の存在だ。
「だけど運転方法が分からない。本の中の知識しかない。」
「それなら、教えてくれるいい人を知ってるぜ。」
直竹は花菜と爽太郎を見ると、ニヤッと薄気味悪く笑った。
その後、「行こう」と直竹が言い、僕たちは緑地を出発した。それが誰なのかは結局のところ教えて貰っていないが、直竹のなかではちゃんとした人がいるらしかった。
緑地から、ずんずんと廃屋への道筋を歩いて行く。食料の入ったリュックは、直竹と爽太郎で背負っていた。中でたぷんたぷんと揺れているのは、飲料だろうか。
「よし着いた。ここだ。」
そこは、さっきも歩いた住宅地の一角で、古い家屋が建っていた。
「大熊のじいちゃん。」
直竹が大声で呼んだ。なるほど、教えを請うのはじいちゃんだったか。爽太郎は合点がいった。
「お、直竹。昼のエロビデオの視聴を止めてまでわしを呼ぶとは、一体何の用だ。」
お決まりの下ネタと共に現れたのは、朝も会った大熊のじいちゃんだった。
「捜し物が見つかりそうなんだ。頼む、車の運転方法を教えてくれ。」
直竹はそう言って頭を下げた。爽太郎たちも、後に続いて頭を下げた。
大熊のじいちゃんは呆気をとられた顔をしていたが、事情が飲み込めたのか、真剣な顔に変わっていた。
「いままで、わしはお前らに女子の扱い方やら女心の極意やらを教えてきた。だが運転方法は犯罪だ。家出か、何かわしは知らんが辞めといた方がええ。世間はそう、甘くはないからの。」
無精ひげをワシャワシャと手で触りながら、大熊のじいちゃんは言った。
「それでも、教えてほしいんです。人生を棒に振る準備は、してきましたから。」
花菜は爽太郎の後ろから出てくると大熊のじいちゃんに強く、その言葉をぶつけた。
じいちゃんは花菜の顔をじっと見る。花菜の双眸には、強い想いが宿っている。大熊のじいちゃんは花菜の瞳を見ると、「分かった」と一言だけ、呟いた。
今まで見たことのない大熊のじいちゃんの真剣な顔に、爽太郎は驚いた。それと同時に、じいちゃんの言葉に、事の重さをひしひしと感じていた。
「家にも、廃車寸前の車が一台ある。ほれ、見てみろ。」
そう言って運転席側のドアを開いた。
「そこがアクセル、こっちがブレーキ。これがエンジンブレーキで、それがウィンカー。こっちがワイパーじゃ。こんな物、習うこともなく最近の子はできてしまう。運転のゲームと同じだからの。」
一通りの説明を受けると、爽太郎は頭の中でなんとなく運転ができるようになっていた。
「ありがとうございました。」
「だがのう、どうしても運転せねばなるまいのであれば、捕まったら大熊健三の名をだせ。そうすれば、お前たちの罪はわしにも来る。」
大熊のじいさんは今まで見たことがないほどの、暖かい笑顔をしていた。もう一度「ありがとうございます」と言うと、じいちゃんは「これで共犯だ」と言って笑った。
大熊のじいちゃんの家で別れを告げると、爽太郎たち三人はどんどんと、廃墟の方へ向かって歩いた。もしかしたらこの景色を見ることはもうないのかも知れない。世の中には、優しい人は意外に身近にいるものだ。直竹と、大熊のじいちゃんの顔が、浮かんできた。
廃墟に着いた。腕時計は午後三時を指している。一番暑くて、一番日の高い時間だ。
直竹と訪れてからそれほど時間は経っていないが、廃屋の崩壊は進み、さっきよりも余計に朽ちているような気がした。
「とりあえず、鍵かけてみようぜ。」
運転席に直竹と乗り込み、直竹が持っていたキーを差し込み思いっきり回した。
何度か、空回りが続く。それでも回し続けると、グウウウンとエンジンから音がした。
古いエンジンが一気に空気を吸い込み、熱を上げるように、轟音と共に動き出したのだ。
「見事にエンジンまで動くんだ……。」
爽太郎は、軽く放心状態だった。直竹も、驚いて言葉を失っている。
花菜はエンジンが動くのを見守ると外から生活スペースへ乗り込み、持ってきた掃除道具で軽く掃除をし始めた。
ある程度掃除が終わると、三人は生活スペースへ集まった。
「……ここまで長かったなぁ。」
花菜は天井に思いを馳せていた。あのときから想っていれば、七年、経っていることになる。
「直竹、大事な話があるんだ。」
埃っぽい空気の中、爽太郎は重く口を開いた。確証はないが今まで直竹に向けた中で、一番真剣な顔をしていると思う。
「これからは、花菜と二人で行かせてほしい。頼む。」
深々と頭を下げた。ここまで手伝ってくれた友人を無下にするのだ。深々と、頭を下げる。
「分かってたよ。俺はここまでって。それでもな、爽太郎。これだけは約束してほしい。絶対、学校に帰って来いよ。」
「ああ。」
親友と熱い握手を交わすと、直竹は何かを花菜の耳元で言い残し、車から降りていった。花菜の顔は、少し赤くなっている。
「そうちゃん。私の夢に付き合わせちゃってごめんね。」
「ううん。僕たちは家族だろ。最後まで行こうじゃないか。」
最後にそう言って、爽太郎は運転席に座った。行こう、高速道路まで。
エンジンブレーキを切ると恐る恐るアクセルを踏んだ。すると車は少しずつ動き出し、前進していく。感覚としては、氷の上を滑っているような、そんな感じだった。
ハンドルを右に回す。するとゆっくりと、車は右へ曲がっていった。ガリガリガリガリ。廃墟の塀に車体が当たっているのか、削れる音がした。
「そうちゃん、当たってる!」
後ろから花菜の声がした。一旦左にハンドルを大きく回し、次に右に回した。すると、ガリガリという音はなく、廃墟から脱することができた。
いよいよ始まった。
下道を走り名古屋南ICから高速へ乗り、名港トリトンまでの短い旅行。それは、人生初の、幼なじみとのドライブデートだ。
田んぼ道を走る。車の操作が不慣れでスピードが遅く、のろのろと、まるで大型の亀のように進んでいた。途中、自転車が一台車の脇をすれ違ったが、本当に怖くて仕方がなかった。もしかしたら僕は人の命を奪ってしまうんじゃないか。その恐怖が、爽太郎を襲った。
「ねぇ、花菜。もし、夢が達成できて、高速道路の上に家を建てれたら、その後なにしたい?」
バックミラーで確認する。花菜は静かに、ソファの上に座っているようだ。恐怖からか体を縮こませ、少し震えているようだ。爽太郎も、怖い。でも花菜には違う恐怖が襲っていた。花菜は近くにあった毛布をかぶるようにして、周りを遮断しているようだった。
幹線道路に入る。車がビュンビュンと飛ぶように走っており、僕もこの中を走るのかと思うと肝が冷えるような感覚がした。信号が、赤から青に変わった。そろそろ行かなくてはなるまい。覚悟を決めて、幹線道路へ大きな車体を進ませる。前の車を見ながら、同じ速度、同じ感覚で車を走らせる。これならいけるかも知れない。爽太郎は、流れに任せてアクセルを踏んだ。一応、スピードメーターを見る。そこには、65kmと表示されていた。
それと同時に、ガソリンメーターが底辺に近いことを発見する。これはまた、大きなミッションだ。爽太郎は止まない苦悩に疲労を感じた。
「花菜、ガソリンがない。お金持ってる?」
ガタガタと体を震わせる花菜に、訪ねる。
「あ、お、お金は、も、持ってきたから、あ、あるよ。」
「じゃあ、近場のガソリンスタンドに入るね。」
ここで、爽太郎は気づいた。そもそもガソリンの入れ方を知らない。大熊のじいちゃんに入れ方を聞いておけば良かった。そんな後悔が、頭の中を巡る。爽太郎は頭をフルに回転させ、とりあえずセルフのガソリンスタンドへ入った。
隣の車の見よう見まねでなんとかガソリンを入れ、花菜からお金を受け取り、支払った。
花菜は、本当に良く車に乗っていると思う。昔の花菜では、絶対にあり得ないことだ。
給油キャップをもう一度確認すると、助手席のドアから運転席へ入り、エンジンをかけた。
ウオオオオン。唸りのような音を上げ、車は前進する。頼む、高速までは耐えてくれ。
爽太郎は天まで届くよう、車の耐久性を祈った。
高速の入り口が迫ってくる。ETCは元から付いていないと踏み、チケットを受け取り、一般のゲートから入場した。
高速の合流は、今までの何倍も怖かった。各々の車がスピードを上げ飛ばしており、一時は合流の成功を神に祈るほどに、爽太郎は恐怖した。
次で行こう。そう決心し、右の車線へ舵を切った。車は、周りの景色と同じように、70kmで走っている。これで、旅の終着点へ、あと一歩だ。安堵からか一気に肩が軽くなるような気がした。花菜は高速に入ってから、もっと恐怖が増しており、ガタガタと、こっちまで聞こえそうなくらいに震えていた。
「大丈夫だから、花菜。」
聞こえるか聞こえないか分からないほどの声で、そう呟いた。
「ねぇ、花菜。旅行、楽しかった?」
「楽しかった!」
母の声。幼い、自分の声。周りの車がビュンビュンと通り過ぎ、それと同じくして周りの景色もビュンビュンと移り変わる。ジェットコースターが見えるところを過ぎたくらいに、お父さんが話し始めたのを今でも覚えている。
「花菜。お父さんはな、この高速の上に、家を建てたいと思ったんだ。」
花菜は、お父さんの言っていることを想像した。自分の家の周りに車が飛び交っている。
「危ないから嫌。」
そう一言呟くとまた、外の景色に齧りついた。夜の高速は、色の付いた丸い光がそこかしこを飛び交っており、まるでイルミネーションを見ているようだった。
「花菜、もうすぐ通る橋の上に、お父さんは家を建てたいと思ったんだ。見ていてね。」
そんなにもお父さんに言わせる景色は一体どんな景色なのだろう。花菜は少し興味が湧いた。
目の前に、白い大きな支柱が現れた。その支柱を支えるように、沢山のロープが結んである。
「ここだ。花菜。父さんはこの景色を見て暮らしたい、って思ったんだ。」
ビュンビュン車が通り過ぎる中窓から見えたのは沢山の、機械やクレーンが立ち並んだ海岸線に、ぽつんと見える高層ビル群。そして真ん中に、星空のように輝く大きな海があった。
「父さんは名港トリトンの景色が本当に、好きなんだ。」
バックミラー越しに見る父さんの瞳は輝いていて、本当に好きなんだな、と実感した。
私もこの景色を見て生活したい、そう思った。
その直後、花菜の乗った車は飲酒運転をしていた後続車に追突され、操作不能になった車はぐちゃぐちゃになるまで名港トリトンの上を転げ回った。救出されたのは当時七歳の花菜だけで、両親は即死だったという。
そこから、花菜は一度も車に乗っていない。
花菜は、あのトラウマのせいで、車に乗れなかった。爽太郎と孤児施設で出会い、そして今までバスを含むすべての自動車に乗れていなかった。今の花菜は相当頑張っているんだと思う。これは爽太郎にしか分からないことだ。爽太郎は花菜の想いに、頬に涙が伝った。
「大府IC」という看板が、ガラスの向こうを過ぎ去って行った。車のダッシュボードにあった地図によると、もうすぐ名港トリトンが、目と鼻の先に待っている。爽太郎は気を入れ直すとさらにアクセルを踏み込み、スピードを落とさないように努めた。
目の前に、白い支柱と、それに結ばれた何本ものロープが、見えてきた。
爽太郎は橋の中心まで車を走らせると、路肩に駐車し、ハザードランプをつけた。
目を覆うように、溢れて止まらない涙を拭く。
「花菜、着いたよ。高速道路の上に、家を建てたんだ。」
窓の外の海は、キラキラと、爽太郎たちを歓迎するように輝いていて、その奥にぽつりと、名古屋の中心地が、そびえ立っている。
爽太郎は車を降り、生活スペースの方に回り乗り込んだ。
花菜は窓の外を見て双眸を輝かせながら、静かに泣いていた。
「そうちゃん。夢が叶ったよ。お父さんと、私と、家族の夢が。そうちゃん。そうちゃん。」
花菜は何度も爽太郎の名前を叫び、大粒の涙を流した。
爽太郎は花菜の隣に行き、腰を下ろした。花菜の瞳は溢れんばかりの涙で輝いていて、目の前に広がる海面のようだった。
きっと、このまま止まり続けていたら、いつかは警察がやってきて逮捕されるだろう。
それでも、爽太郎は車を走らせないと決心していた。この景色が、花菜の旅の終着点なのだ。長かった七年間。思い返すだけで様々な思い出がよみがえり、心が、熱くなる。
爽太郎は花菜を抱きしめると、花菜の横顔に、話しかけた。
「花菜、良かったね。頑張ったね。」
「そうちゃん。」
花菜は決壊したダムのように涙を溢れさせ、ぽつぽつと、雨を降らせた。
これじゃあ晴れていていも意味ないな。
十一日連続の雨は、サイレンが鳴るまで、静かに、地上にしたたり落ちていた。